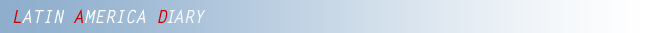明けて、4月29日。今日から早速仕事が始まる。契約は15日間。その間にラディオ・カラカス・テレビ局音楽番組「エル・ショウ・デ・レニー」14本に出演すること、と示されている。
これは、軽妙なウイットとユーモアでベネズエラのみならず他のラテン諸国にも知られるレニー・オトリーナがホストの、ベネズエラ版エド・サリバン・ショウといったものである。毎週、日曜日は夜8時から、1時間半、月曜から金曜は正午より1時半まで。昼休みが長くオフィスに勤める人々も自宅で食事をする習慣のある南の国だから、昼のこの時間帯はゴールデン・アワーで、視聴率も高い。常時3、4人の外国からのゲストが出演し、日本にも知られるスターの殆どがこの番組に一度はでている。
この日は5月2日、私のデビューの日の分をビデオ撮りするので、指定の2時間も前から緊張してスタジオ入りしていたが、同日がさようならの日のゲストも何人かいて、夜遅くまで時間がかかり、私はもっぱら待たされて、それだけに他のゲストをじっくり見ることもできた。
「シガモス・ぺカンド」をリバイバルヒットさせた、チリのトリオ、エルマノス・アリアガータ。この1965年、わが伊藤ゆかり嬢とともにサン・レモ音楽際で「恋する瞳」を歌い、入賞したイタリーの若手ブルーノ・フィリピーニ。ベネズエラのクアルテート、ロス・ナイペス。このグループの紅一点ミルタ・ペレスは、のちにソロ歌手になり、69年、ブエノスアイレスの音楽祭で「ラ・ナベ・デル・オルビート(忘却の小船)」をひっさげ優勝した。わが国では、ホセのヒット曲として知られているが、本家はこちらである。後年彼女と共演し、その成長ぶり感嘆したものである。
以上3組のゲストは、この年のヒット曲をかかえていることもあり、スタジオでもファンにかこまれて熱演していたが私を一番喜ばせたのは、キューバ出身の“エル・グアラチェーロ”ロランド・ラセーリエである。グアラチェーロとはアラーチャ歌手のことだが、彼の場合は定冠詞がついているのにご注意。これは同じキューバ出身のセリア・クルスがラ・グアラチェーラと愛称されているのに対するものである。
ついでながら、キューバ人の大スターといえば、トロピカルものを得意とするセリア・クルス、ミスター・パパルーことミゲリート・バルデス、サルサの女王ラ・ルーべ、このロランド・ラセリーエ、ボレロやバラータではオルガ・ギジョー、ブランカ・ローサ・ヒル、異論を唱える人もあろうが(1965年頃)、以上を6大スターと呼べよう。幸運にも私は後年ラセーリエ以外の5人とも共演することが出来たし、いずれゆっくり記すとして、当面はロランドのことだ。
彼はトレードマークの鳥打ち帽を冠りリハーサルからグアグアンコのリズムに乗って調子がいい。日本のテレビ・スタジオのあの張りつめた雰囲気しか知らない私は、この日スタジオ入りした時からあまりものリラックス・ムードに驚かされていたのだが、これはまたどうだろう流石はカリブ海に面した国のこと、キューバン・リズムが流れだすと、スタジオ中がとたんに浮かれ出し、かけ声が乱れとぶ。公開録音ではなく、スタッフのほかには30人ほどの見学者があるだけだが、カメラマンまで腰をふり出した。キューバの黒人独特の、張りのあるラセーリエの声は、日本で聴いたレコードどおりである。
ラテン音楽の中でも、特にキューバのトロピカルものに心酔していた私は、いつしか見学の女性と踊り出していた。それまで大人しく、というよりむしろおどおどと見学していたこの東洋の少年?
(実際私は16歳ぐらいにみられていたらしい)が、いきなりつかれたように踊り出したので、スタジオの連中が注目し出す。その視線を意識して、踊りがますますオーバーになる(この私の見せびらかし根性の愚かさは今でも変わらない)。
曲が間奏になって、ロランドがアドリブで早口に
「このチニート(東洋の男の子)は、サボール・トロピカル(トロピカルの味)を持っているね」
とふざける。司会のレニーがすかさず「チコ、エル・ノ・エス・チーノ、エス・ハポネス(君、中国人じゃないよ、日本人だよ)」
と、これもリズムに乗って言うが、ロランドを真似てカリブ海地方の早口となりまで言うから「チコ、エル・ノ・エ・テーノ、エ・ハポネ」と聞こえる。
ラテンファンならご存じの方も多いと思うが、ベネズエラを含めカリブ海の国々のスペイン語は非常に早口で、単語の途中や語尾にくる単独のSは殆ど発音しない。私は今でもこのなまりがなおらないが、メヒカーナそのもののマリキータ帆足さんとふざけてスペイン語でやりとりする時は大変。おたがいに自分の方が正しいと張り合い、いつも最後に「ビバ・メヒコ!」「ビバ・ベネズエラ!」とどなり、大きな声を出した方が勝ちとなる。反対に、長年日本にいるメヒコ人2人が東京弁と大阪弁で話し合っているのを聞いて笑ったことがあるが・・・
ロランドのショウは、このように冗談ばかりが続き、スタッフも踊っているので、いつになったら本番のビデオ撮りかと他人ごとながら気にしていたら、もう本番中だと言われてびっくり。トロピカルものは、このような雰囲気作りが歌手を助ける。
流石にダテに黒いだけではない。私のように、これみよがしに暴れなくても、ほんの2・3歩動き、腰をひねるだけでリズム感があふれ、サマになる。
私が初めて「サルサ」ということばを耳にしたのもこの時だ。カリブ海諸国のトロピカル音楽、いや今はやりのサルサミュージックと呼ぼうか、これらには必ずかけ声が入る。この時にも見学者たちが、さかんに「サボール!」「アスーカ!」「アイ・ナマ」そして「コン・ムーチャ・サルサ(ソースをたくさんきかせて。つまり、激しくやって)」と歌手にはっぱをかけていた。
トロピカル(サルサ)の歌手が歌う時の掛け声は、トレードマークみたいなものがあり、セリア・クルスは、よく「アスーカル!(砂糖)」「サボール!」「バージャ!(行け)」、ラ・ル―べは「アーイ」と一声感極まったような、セクシーなダミ声を出す。このロランドは「デ・ペリークラ!(文句なし)」がおはこ。
いつまでも続くキューバン・メドレーを耳に、私は明日の自分の歌のことを考え、武者ぶるいしていた。
余談だが、サルサというネーミングはこの当時一般ではなく、カラカスから同時にニューヨークに渡り、レコード会社かニューヨーク発としてマスメディアにとり上げたので、広く知られるようになったと思われる。

秋の、ある午後の編集部で、緊急編集会議が開かれた。病気療養中のラテン歌手YOSHIRO広石から分厚い原稿が寄せられたからである。ゴー・サインが出された。“ラテンアメリカで成功しました”の良いことづくめではない内容が、われわれスタッフの心をとらえたのである。違うだろうか?
編集子は、彼を訪ねてみた。
想像していたよりも、ずっと元気そうな姿
――――もとより当人の苦しみが他人である者に分かりはしないが――――――――が、まず嬉しかった。
「当時だったから恥ずかしくて書けなかった、人に話せもしなかったことも今なら書けると思うんですよ」
と彼は言う。「カラカス到着のこともそうですが、メヒコで食いつめちゃった時のことだとか・・・・・」
広石クンは若い。だから編集子も言った、
「あなたの気持ちが許すのなら、なんでも書いて下さい。でも、あなたは再起するのだから、マイナスにはならないようにね。もっとも、その辺は編集部で気をつけて削除するなり配慮しますから、気にかける必要はありませんよ」
海外での歌手生活はきびしい。その赤裸々な姿は読者に強い印象を残すに違いない。だが、編集者は願っている。病いもいえてカムバックした彼が“書くのはもう止めた。ボクは歌うんだから”と言う日を。
彼への励ましの手紙は、どうぞ編集部へ。アミーゴス、YOSHIROの歌を早く聞きたいだろ!