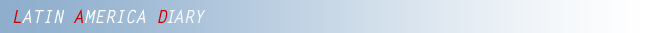私の契約も終わりに近づいたころ、サルサの女王ラ・ルーペが新しいゲストとして訪れた。ニューヨークを本拠に活躍する彼女は、よくセリア・クルスと比較されるが、ニューヨークでザ・クイーン・オブ・ラテン・ソウルと呼ばれるようにセリアよりソウルっぽく、センセーショナルな意味では彼女の方が若い人たちに受けがよい。ただ、セリア・クルスがラテンアメリカ諸国どこへ行っても、トロピカルの女王※まだサルサという言葉が一般でなく彼女がサルサの女王と言われるようになったのは1970年代に入ってからである。
として君臨しているのに較べ、ラ・ルーペはその強烈な個性ゆえにラ・ローカ(クレイジー)だと言う人もあり、国によって人気の差がある。
スタジオでは、リハーサルの一部しか見られなかったので、ある夜彼女のクラブ・ショウを観に行った。
「シ・ブエルベス・トゥ(もしあなたが帰って来たら)」という、タイトルはスペイン語だが、フランスの曲がオープニングになっている(この曲は、私のメヒコでのデビュー曲になった)。少しフラット気味に聞こえるので、キィが高いのかと思ったが、それが彼女のクセであることに気がついた。ダミ声をぶつけるようにしてシャウトする唱法なので、ひとごとながら疲れはしないかと心配したが、実に一時間半にわたり、歌い、踊り狂ったのである。
オープニング・ナンバーをろうろうと歌いあげたあとは、すぐさま三つのパーカションがプエルト・リコのリズム、プレーナをきざむ。早くも客は浮かれ始める。ラ・ルーペは中々歌わず、早く口でしゃべり続ける。私にはまったく分からないが“ラ・ボンバ(爆弾娘)”のニックネームも持つ彼女の自己紹介もかね、
「これからボンバ(爆弾)をいくつも落とすけど、皆さんが死なないことを祈るわ」
と言ったらしい。
それから一時間半の、なんとすさまじかったことか。曲はたまにスロー・ボレロも入るが、殆どアップテンポのサルサそのもの。
4曲目のグラーチャ・ソンあたりから、彼女の目が気違いじみて来て、いきなり靴とストッキングを脱ぎ、放り投げる。先に“踊り狂う”と書いたが、むしろステージをころげまわると言った方がよい。ボンゴセーロ(ボンゴ奏者)の髪の毛をひっぱる。ピアニストの頭をボンゴの代わりに叩く。まるでブラジルの密教カンドンブレの儀式を見るようだ。
その後の彼女のヒット曲「ケ・テ・ぺディ(あなたにねだったもの)」は思いっきりスローで、官能的に歌いあげる。曲の途中の「アイ・アイ・アイ」という感きわまった歌い方がワイセツだと、その当時は問題になったと聞くが、メロディの美しい曲でもあり、機会があればCDを聞いてもらいたい。
曲がまだ早いサルサ風になり、
「皆さん、ちょっと暑いので失礼!」
と言うやいなや、なんと美しい黒髪のかつらをむしりとり、つけまつ毛までとったではないか。淡谷のり子先生を上まわる濃いアイラインは汗ではげ、お気の毒な素顔のラ・ルーペ。
客は興奮、はじめはただびっくりの私も、やがて狂ってしまい、精根つき果ててステージから消える彼女を追っかけて行った。
ラ・ルーペのステージは、いつもこのようであるらしい。時にはストッキングどころかパンティまで脱いでしまい、おカタイ国、例えばメヒコなどではひんしゅくを買い、人気どころか、舞台に出させてもらえないとも聞く。こんなところから、国によって人気の差が出るわけだ。

私の短いベネズエラ滞在中には、他局の番組にもメヒコからロス・パンチョスやマルコ・アントニオ・ムニスが出演していたが、皮肉なことにゲストが出演していたが、皮肉なことにゲストよりも地元カラカスの歌手がの何人かの方が、どう見ても音楽的に優れていて、ある日ふとそのことをベネズエラの一歌手にもらすと、待ってましたとばかり、
「この国は外タレに弱いんだよ。石油で金があるので、出演料だって他の国よりずっと多く出すし、そのためわれわれの仕事場はせばめられているんだよ。本当に良いゲストなら歓迎だけどね」
とボヤく。人気に酔いしれていた世間知らずの私は、それがもしかしたら私への皮肉であるかもしれないと気づく余裕は、とてもなかった。
我が国で知られているラテン歌手の殆どはまずメヒコでヒットした歌手の殆どはまずメヒコでヒットした歌手たちであるが、この年知ったベネズエラの男性歌手たちであるが、この年知ったベネズエラの男性歌手ホセ・ルイス・ロドリゲス(七四年ヤマハ世界歌謡祭で歌唱賞受賞)、女性ではミルラ・カスティジャーノ(六五年メヒコ音楽祭で「コン・ロスブラーソス・クルサードス」を歌い入賞)などは、もっともメヒコで活躍し、我が国ファンにもなじみになってもらいたい、立派な歌手である。
五月十六日、ラディオ・カラカス・テレビとの契約も終わり、私は連日パーティやら、コロンビア、パナマ、ペルーなど巡演の打ち合わせ、レコーディングの話などで、最早正気の沙汰ではないほどに浮かれていた。サミー・デビィス・ジュニアやポール・アンカらも出演したという単純な理由から、まるで彼らと同じレベルの人気者になったような錯覚におち入り、その人気をためすため、昼となく夜となく出歩いては、サインに群がる人波の中で酔いしれた。もっとも、実力以上に思いがけなく人気の出た日本のジャリタレに群がるプロダクション同様、海千山千のマネージャーが私のこの“変な人気”で儲けようと、毎日私のホテルに来ては、いっしょにはしゃいでいたことも確かだ。
おろかと言ってしまえばそれまでだが私は歌の文句のように「恐いくらいに幸せ」だった。一夜、家族にこの喜びを手紙に書きながら、羽田を発つ日、私に逢うことも出来ず淋しく死んで行った父を思って泣いた。
「夏のトウフとスターの人気は三日ともたぬ」ということばが、身にしみて分かったのは、その後間もなくメヒコに発ってからである。そして、外国で歌っていく厳しさなども、分かってくるようになるのだが・・・・・・
※レニー・オトリーナはその後サンレモ音楽祭の司会や広域に活躍し、ベネズエラ大統領選にも立候補し、ヘリコプター事故で亡くなったが、暗殺されたとも言われている。